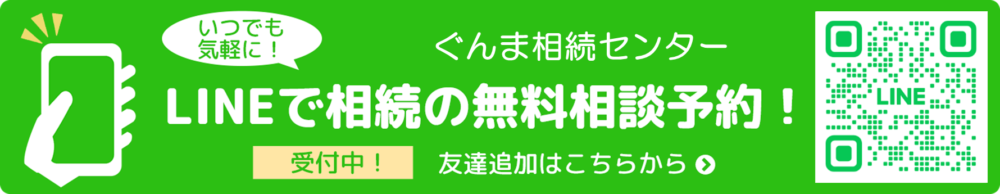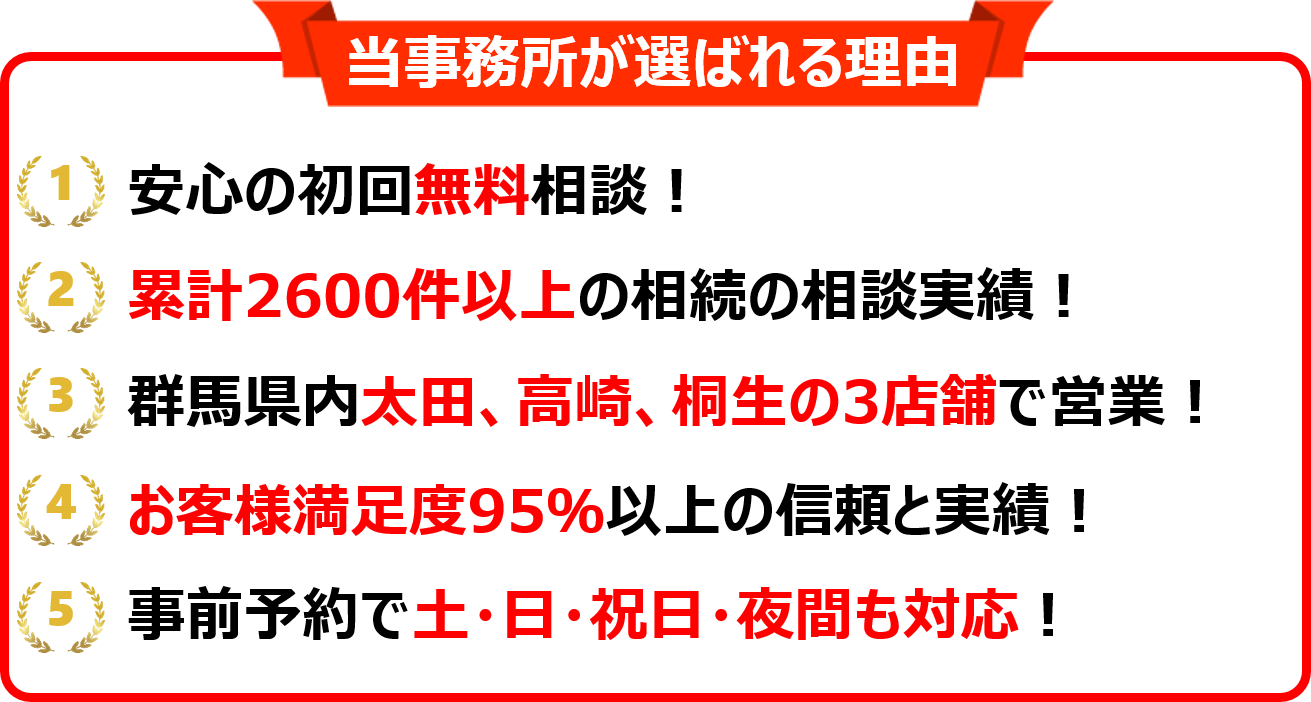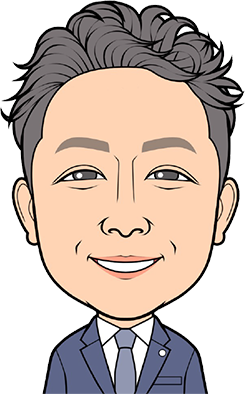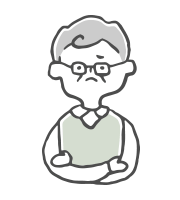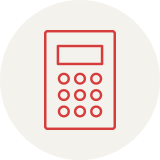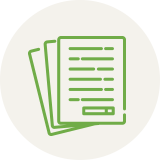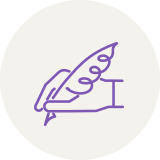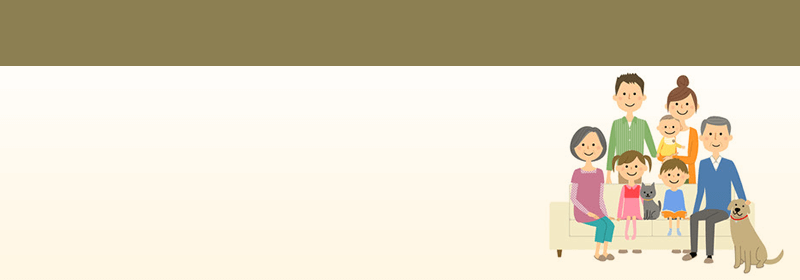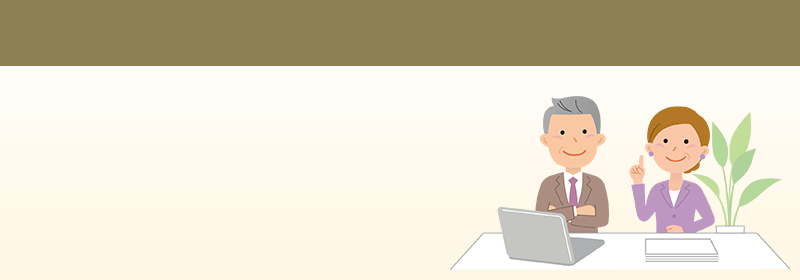再婚相手の連れ子に相続権は?トラブルを回避する方法を司法書士が解説!

「自分が亡くなった後、長年連れ添ったパートナーの連れ子に財産を残してあげたい」 「再婚相手が亡くなった場合、自分の子どもは相続できるのだろうか?」
近年、再婚家庭の増加に伴い、このような「連れ子の相続」に関するご相談が司法書士事務所にも多く寄せられています。
大切な家族だからこそ、財産を巡るトラブルは避けたいもの。しかし、法律上のルールを知らずにいると、思わぬ形で家族が傷つく事態になりかねません。
本記事では、相続の専門家である司法書士が、再婚相手の連れ子の相続権について、法的な原則から具体的な対策、そして起こりがちなトラブルとその回避策まで、分かりやすく解説します。
目次
【結論】何もしなければ、再婚相手の連れ子に相続権はない

まず、最も重要な結論からお伝えします。あなたが亡くなった場合、再婚相手の連れ子には、原則としてあなたの財産を相続する権利はありません。
なぜなら、日本の法律(民法)では、相続権が認められるのは「法律上の親子関係」がある人のみと定められているからです。
法律上の親子関係とは?
・実の親子(血の繋がった親子)
・養子縁組をした親子
再婚相手とその連れ子は、たとえ長年一緒に暮らし、実の親子同然の深い絆で結ばれていたとしても、再婚しただけでは法律上の親子関係は発生しません。 そのため、あなたの「法定相続人」にはなれないのです。
では、大切な連れ子に財産を残すには、どうすれば良いのでしょうか。ご安心ください。生前に適切な手続きを行うことで、財産を引き継がせることは可能です。
連れ子に財産を渡すための4つの具体的な方法
連れ子に財産を残すための代表的な方法は、以下の4つです。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況や希望に最も合った方法を選びましょう。
養子縁組は、連れ子と法律上の親子関係を結ぶ手続きです。これにより、連れ子はあなたの「実子」と全く同じ立場で相続権を持つことになります。
相続分: 他の実子と同じ割合で財産を相続します。
代襲相続: もし養子(連れ子)があなたより先に亡くなっていた場合、その子ども(あなたから見て孫)が代わりに相続する「代襲相続」も認められます。
注意点
実親との関係: 普通養子縁組の場合、実の親との親子関係も継続します。つまり、連れ子は「実親」と「養親(あなた)」の両方の相続権を持つことになります。
他の相続人への影響: 養子縁組をすると法定相続人が一人増えるため、他の相続人(例えば、あなたの実子)一人ひとりの相続分は減少します。事前に他の家族の理解を得ておくことが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
方法2:遺言|財産を「遺贈」する
養子縁組はしたくない、あるいはできない事情がある場合でも、「遺言」によって特定の財産を連れ子に渡すことが可能です。これを「遺贈(いぞう)」と言います。
メリット: 「自宅の土地建物は連れ子に」「預貯金の半分を連れ子に」というように、渡したい相手と財産を自由に指定できます。
注意点(遺留分)
兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、法律上最低限保障された相続分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。
連れ子に全財産を譲るような遺言を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、後に金銭を請求される(遺留分侵害額請求)トラブルに発展する可能性があります。遺留分に配慮した内容にすることが非常に重要です。
司法書士からのアドバイス
遺言は法的に有効な形式で作成しなければ意味がありません。特に自筆の遺言は要件が厳しく、無効になるケースも散見されます。トラブル防止のためにも、確実な「公正証書遺言」の作成を強くお勧めします。
当事務所では、文案の作成から公証役場での手続きまで、トータルでサポートいたします。
方法3:生命保険|遺産分割の争いを避ける
生命保険の死亡保険金を活用するのも、非常に有効な手段です。
メリット: 契約時に死亡保険金の受取人を連れ子の名前に指定しておけば、その保険金は民法上の相続財産とは見なされません。 そのため、遺産分割協議を経ずに、連れ子が直接、速やかに現金を受け取ることができます。相続争いの対象になりにくいのが最大のメリットです。
注意点
受取人が誰になっているか、定期的に契約内容を確認しておきましょう。
方法4:生前贈与|生きているうちに気持ちと共に渡す
生きているうちに財産を贈与する方法です。
メリット: あなたの意思で、確実に財産を渡すことができます。「ありがとう」という気持ちと共に直接渡せるのは、生前贈与ならではの利点です。
注意点(税金)
個人からの贈与には贈与税がかかります。ただし、年間110万円までの贈与であれば非課税となる「暦年贈与」の制度があります。
多額の財産を一度に贈与すると高額な贈与税が発生する可能性があるため、計画的な利用が必要です。
【事例で見る】連れ子相続でよくあるトラブルと回避策

対策を怠ったことで、実際に起きてしまったトラブル例を見ていきましょう。
ケース1:口約束だけで対策せず…
Aさん(夫)は妻Bさんと、Bさんの連れ子Cさんと長年暮らしていました。
Aさんは生前、「Cのことは実の子だと思っている。財産はBとCに残す」と話していましたが、養子縁組も遺言もないまま急逝。Aさんには前妻との間に子Dさんがいたため、相続人は妻Bさんと子Dさんになりました。Cさんには一切の相続権がありません。
Dさんは「Cさんは法律上の相続人ではない」として、法定相続分通りの遺産分割を主張。BさんとCさんは、Aさんの自宅に住み続けることも難しくなってしまいました。
回避策: Aさんが生前に「Cを養子にする」か「Cに財産を遺贈する旨の遺言書を作成する」という対策を取っていれば、Cさんは財産を受け取ることができました。
ケース2:実子の遺留分を無視した遺言で…
Eさん(父)は、後妻Fさんとその連れ子Gさん(養子縁組済み)と同居していました。
Eさんには先妻との間に実子Hさんがいます。Eさんは「全財産を、身の回りの世話をしてくれたGに相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。
これを知った実子Hさんは、自分の遺留分が侵害されたとして、Gさんに対して遺留分侵害額請求の調停を申し立て、家族間の深刻な争いに発展してしまいました。
回避策: Eさんが遺言書を作成する際に、専門家に相談し、実子Hさんの遺留分に配慮した内容にしていれば、トラブルを避けられた可能性が高いです。
まとめ|大切な家族のために、今できる準備を
今回は、再婚相手の連れ子の相続について解説しました。
何もしなければ、連れ子に相続権はない。
財産を渡すには「養子縁組」「遺言」「生命保険」「生前贈与」の4つの方法がある。
どの方法にもメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合わせた選択が重要。
他の相続人、特に実子の「遺留分」への配慮がトラブル回避の鍵となる。
「うちの場合はどの方法が一番良いのだろう?」「何から手をつければいいか分からない」
そう思われた方は、ぜひ一度、相続の専門家である司法書士にご相談ください。ご家族の状況やご希望を丁寧にお伺いし、円満な相続を実現するための最適なプランをご提案いたします。
家族の形が多様化する現代だからこそ、法律の知識を持って、早めに、そして確実に対策を講じることが、あなたの愛する家族全員の未来を守ることに繋がります。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
-
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
主な相続手続きのメニュー
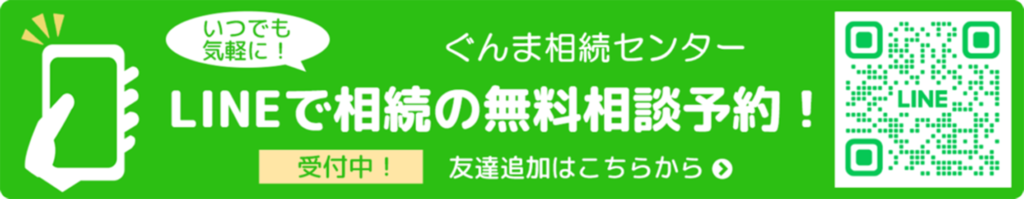
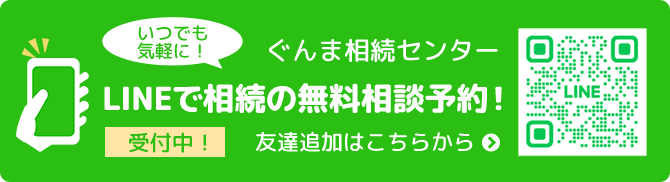
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
太田・高崎・桐生で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで